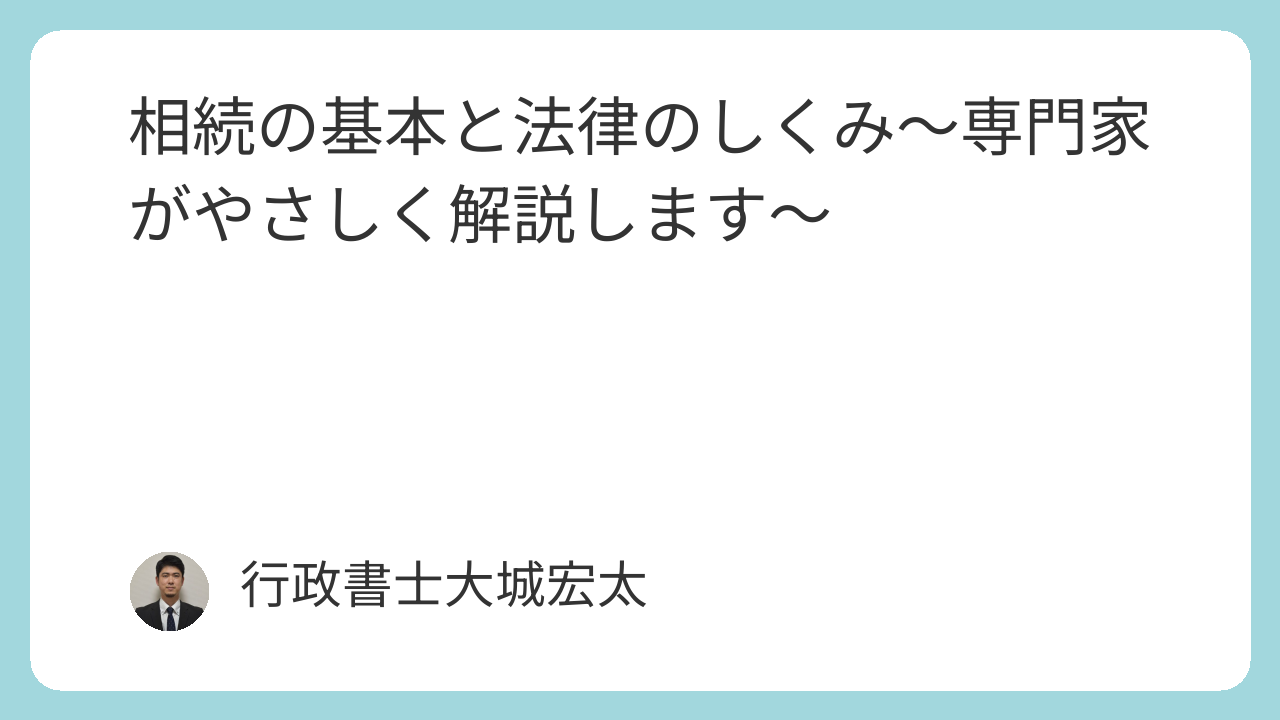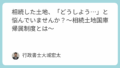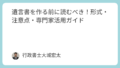相続は誰にでも関係する、身近な問題
こんにちは。行政書士の大城です。
日本は世界でも類を見ない”超高齢社会”に突入し、それに伴って多くの課題が浮き彫りになっています。中でも「相続」は、どなたにとっても避けられない問題です。
親が亡くなったとき、配偶者が他界したとき、自分の財産の行方を考えるとき――相続は人生の節目に突然訪れます。ところが、法律や手続きの話となると「難しそう」「何から始めればいいの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、法律の専門家である行政書士の立場から、相続の基本知識、流れ、注意点、そして専門家がサポートできることまで、やさしく丁寧にご紹介します。
相続のしくみを知ろう
相続とは?
相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産(資産と負債の両方)を一定のルールに基づいて引き継ぐことをいいます。
法律上の定義 として、民法第896条では以下のように定められています。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。
この条文から分かる通り、相続人は単に財産をもらうだけでなく、借金などの義務も含めて引き継ぐことになります。つまり、「いいものだけをもらえる」とは限らない点に注意が必要です。
相続人って誰?配偶者や子どもだけじゃない?
相続人となる人の順位は、民法に明確に定められています。
- 第1順位:子(子がいなければ孫)
- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(甥姪による代襲あり)
そして、配偶者は常に相続人になります(民法第890条)。
相続財産とは?
相続財産には以下のようなものがあります:
- プラスの財産:現金、預貯金、不動産、有価証券、自動車など
- マイナスの財産:借金、ローン、保証債務など
また、祭祀財産(墓地、仏壇など)や生命保険金の受取人指定があるものなど、相続財産に含まれないものもあります。
トラブルを避けるためのポイント
遺言書は相続の道しるべ
遺言書は、被相続人の最後の意思を明確にするもので、相続のトラブル防止に非常に有効です。
種類には以下の3つがあります:
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
令和元年より、自筆証書遺言の法務局保管制度も始まり、利便性が向上しました。
遺言書については、作る前に読んでおくべき注意点などを下記のリンクにまとめております。
遺言書の書き方と保存方法|相続トラブルを防ぐ基礎知識 | おきなわ外国人サポートブログ
相続の基本ステップ(7つの流れ)
- 死亡届の提出(7日以内)
- 遺言書の有無確認と検認手続き(家庭裁判所)
- 相続人の調査・確定(戸籍収集)
- 財産調査(金融機関、登記簿謄本等)
- 遺産分割協議(民法906条~)
- 相続税の申告・納付(相続税法)
- 名義変更・登記申請(法務局など)
相続放棄と限定承認という選択肢
借金などの負債が多い場合、「相続放棄」や「限定承認」が可能です。
民法第915条
相続開始を知った日から3ヶ月以内に、承認または放棄の意思表示をしなければならない。
- 相続放棄:財産も借金も一切引き継がない
- 限定承認:プラスの財産の範囲内で借金を返済
期限があるため、早めの判断が求められます。
遺産分割の話し合いは慎重に
遺産分割には、相続人全員の合意が必要です。合意に至らない場合は、家庭裁判所による調停や審判に進むことになります。
遺産分割協議書については、下記にリンクにまとめています。
遺産分割協議書の基本と作り方|行政書士がわかりやすく解説 | おきなわ外国人サポートブログ
安心のために今できること
よくある相続トラブル
- 遺言書が不明確で争いに
- 相続人の所在が分からない
- 相続税の申告漏れ
予防策
- 遺言書の作成と保管
- 相続人の情報整理
- 生前贈与や家族信託の活用
こうした問題を防ぐために、日頃からの備えが大切です。
行政書士のサポート
行政書士は、相続に関する各種手続きをサポートします。
- 戸籍調査と相続人確定
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関や役所提出用の書類作成
特に戸籍の取得や調査、図表の作成は煩雑で、専門家に依頼することでスムーズに進みます。
おわりに
相続は、誰にとっても他人事ではありません。正しい知識と備え、そして信頼できる専門家の助けがあれば、円満な相続は実現できます。
「いざという時に慌てないために」――その第一歩を、今から踏み出しませんか?
【おきなわ外国人サポート行政書士事務所】では、初回相談も受け付けております。
詳しくはこちら →おきなわ外国人サポート行政書士事務所