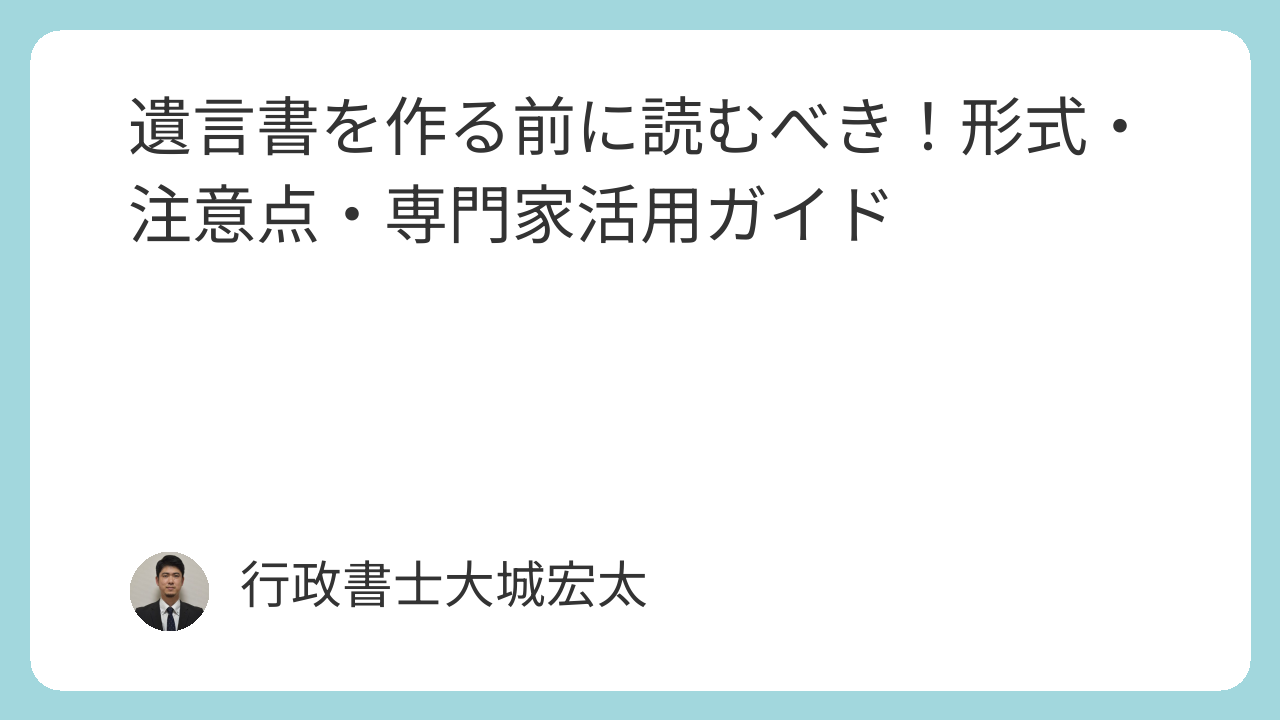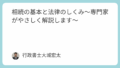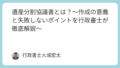なぜ遺言書がいま、必要なのか?
相続にまつわるトラブルは後を絶ちません。例えば、「親の預貯金、一部だけ記録されていたが他に財産が発覚し、兄弟姉妹が激しく対立した」「遺言の日付が『吉日』だけで記されたため無効となり、全く意図しない遺産分割になってしまった」など、実際に家族が傷つく事例も珍しくありません。
こうした悲しい結末を避けるために、遺言書は「自分の死後に伝えたい想いを、法的に確かな形で残す手段」として、今注目を集めています。本記事では、遺言書の種類・書き方・陥りがちなミス・保存・運用・行政書士の活用方法まで、分かりやすく章立てで解説していきます。
まずは「遺言書の種類」
日本では、民法で定められた普通方式遺言が主に3つあります。
自筆証書遺言
遺言者が全文を手書きし、日付・署名・押印を行う形式です。財産目録はパソコンでの作成も可とされ、費用もかからず手軽です。しかし不備があると無効になる他、紛失・盗難・書き換えのリスクもあります。さらに相続開始後には家庭裁判所の「検認」手続きが必要です。(※2020年7月開始の遺言書保管制度により、法務局へ保管することで検認は不要となっています。)
公正証書遺言
遺言者が公証役場で証人2名以上立ち会いのもと、公証人に内容を口述し、書面化してもらう方式です。原本は公証役場に保管されるため検認不要で、最も信頼性が高いといえます。ただし、公証人の手数料・証人調整などのコスト・手間があるのが欠点です
秘密証書遺言
本文を秘匿したまま、公証人に「存在のみ」を証明してもらう方式です。内容は本人や将来の閲覧者の手元に残ります。形式要件が複雑で、自筆署名・押印・証人立会い・検認などが必須で、あまり利用されません。
なお、「特別方式遺言」は、戦時や船舶航海中など通常の方式が困難な場合に限り例外的に認められますが、通常はあまり使われません。
実際の「遺言書の書き方」
遺言書を書く際には以下のステップを踏むのが基本です。
1)方式の選定
ご自身の状況(健康状態・財産内容・家族構成・費用負担)を踏まえ、上記の3方式から選びます。
2)相続人・財産の調査
相続人を戸籍から確定し、財産目録を作成して不動産・預貯金・株式等を漏れなく把握します。負債も記録し、内容を網羅的に明記することで後から相続人が困ることを防げます
3)自筆証書遺言の書き方(例)
遺言者 ◯◯◯◯(昭和○年○月○日生)は、以下の通り遺言する。
第1条 遺言者の預貯金○○銀行□□支店普通預金口座1234567の預金を、長男 ◯◯◯◯ に相続させ る。
第2条 遺言者の所有する沖縄県那覇市△△丁目△番△号の土地建物を、長女 ◯◯◯◯ に相続させる。
第3条 上記以外の財産がある場合は、すべて配偶者 ◯◯◯◯ に相続させる。
令和◯年◯月◯日
住所 沖縄県那覇市○丁目○番○号
遺言者 ◯◯◯◯ ㊞
※目録以外は、自書を必要とします。目録を自書しない場合は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければなりません。
4)公正証書遺言の流れ
①内容を整理し、公証人が正確に筆記できるよう書き起こした原案を用意し、遺言者+証人2名で公証役場へ赴きます。
②遺言者が遺言の主旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述をもとに文章を作成します。
③これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、正確であることを承認した後、各自これに署名し、印を押します。
※費用や流れ、必要なものなどを事前に各公証役場へ確認しましょう。
5)秘密証書遺言の手順
①証書の内容は代筆可ですが、遺言者がその証書に署名・押印を行い、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印します。
②遺言者は、証人2人以上と公証人立ち会いで封書を提出し、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。
③公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押します。
封印が改ざんされていないことを検認で確認するのが重要です。
失敗しやすい「間違いやすいポイント」
①日付の不備
「吉日」や「80歳になる日」のような不特定日は無効になります。必ず「2025年6月1日」など具体的に記載が必要です。
②署名・押印の漏れ
押印忘れは致命的で無効になるケースもあります。
③財産記載が曖昧
「全財産」と書くと不動産・現金・負債まで含むことになってしまいます。特定の財産を受け取らせたい場合は対象を明記しなければなりません。
④複数遺言の矛盾
複数の遺言書を作成する場合、最新版のみ有効というわけではなく、どれを採用するか揉めるケースが多いため、「この遺言が最新版である」と明記するか、古いものを撤回する旨を示す必要があります。(通常、矛盾が生じている場合は「最新版」が法的には優先されますが、矛盾がない場合は両方の遺言が併用される場合があります。)
⑤証人の資格
公正・秘密証書遺言において証人が未成年、推定相続人やその配偶者・直系血族だと要件を満たさず、その遺言は無効になります
⑥検認忘れ
自筆・秘密証書遺言は家庭裁判所の検認手続きを必須で行わないと、封印を破れず相続に進めません。
⑦偽造・紛失の懸念
手元管理だと盗難や偽造の危険があります。次節で紹介する制度活用をおすすめします。
保存と運用のポイント
◉ 自筆証書遺言書保管制度(法務局)
2019年民法改正、2020年7月開始の制度で、全国312か所の法務局に本人が持参して遺言書原本+画像データを預けることができます。形式チェック・紛失防止・検認不要・遺言者指定通知などのメリットがあります 。利用には手数料や相続後閲覧料、証明書代が別途かかります 。
◉ 公正証書遺言の保管
原本は公証役場が厳重管理します。そのため、相続人は謄本を取得することができ、検認が不要で改ざんもありえません。
◉ 見直しの習慣
家族構成・財産・制度(税制・法改正)は変化します。定期的に内容を見直し、必要時に修正・再作成することが重要です。
◉ 意図の共有
遺言書の存在や場所を、相続人にある程度伝えておくことで、死後に混乱を避けられます。交代的に信頼できる相続人に情報を共有しておくのが望ましく、付言として想いを綴るのも良いでしょう
行政書士への依頼で失敗しない遺言書作成
行政書士へ依頼すれば、以下のようなメリットがあります。
1.相続関係と財産の調査:戸籍・財産目録の整理を依頼でき、財産漏れのリスクを減少させます。
2.方式チェック・書式確認:方式不備による無効の危険を事前に排除できます。秘密・公正証書遺言でも証人にすることができます。
3.遺言執行者としての支援:執行者に選任すれば、相続手続き全般を代行可能です。初期段階から遺言の内容を実現するまで一貫支援が可能です。
想像してみてください。遺言がある場合とない場合
これまで、遺言書の種類や書き方、注意点についてお伝えしてきましたが、ここで少しだけ想像してみてください。
たとえば、ある家族にご高齢の親御さんがいらっしゃったとします。子どもたちはそれぞれ家庭を持ち、遠方に暮らしており、普段はあまり会う機会がない。親御さんには、不動産や預貯金がいくらかあり、「自分が亡くなったら、子どもたちがうまく話し合って分けてくれるだろう」と思っている。
しかし、もし何の準備もなくその日が来たら…。
相続人である子どもたちは、「通帳はどこ?」「土地の名義は?」「親はどうしてほしかったの?」と、不安と戸惑いを抱えながら手続きを進めることになります。お互いに悪意はなくても、意思疎通がうまくいかず、気まずくなってしまうことも。
一方で、簡単なものであっても「遺言書」が残されていたらどうでしょうか。
「この預金は長男へ」「この家は配偶者へ」「その理由は…」と、遺言書の中で本人の意思が伝えられていれば、遺族はそれを手がかりに安心して手続きを進めることができます。
遺言書は、金銭の話を超えて、「どう生きてきたか」「誰を大切にしていたか」を伝える言葉にもなり得ます。
難しく考えすぎなくて大丈夫です。
「自分が死んだあと、家族が困らないように、何か一言でも伝えられないだろうか?」
そんな気持ちから、遺言書は始まります。
遺言書は、未来への思いやり
遺言書というと、「自分にはまだ早い」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。けれども実際には、元気なうちだからこそ、自分の意思をきちんと形にできるのです。
特別な法律知識がなくてもかまいません。自筆で簡単に書き始めることもできますし、「まず何から手をつければいいのか?」と迷うときは、行政書士のような専門家に一言相談してみるだけでも、ずいぶん気持ちが楽になるものです。
最後に、この記事が遺言書について考える小さなきっかけとなれば幸いです。ご自身やご家族にとって最善の形を、一緒に探していきましょう。