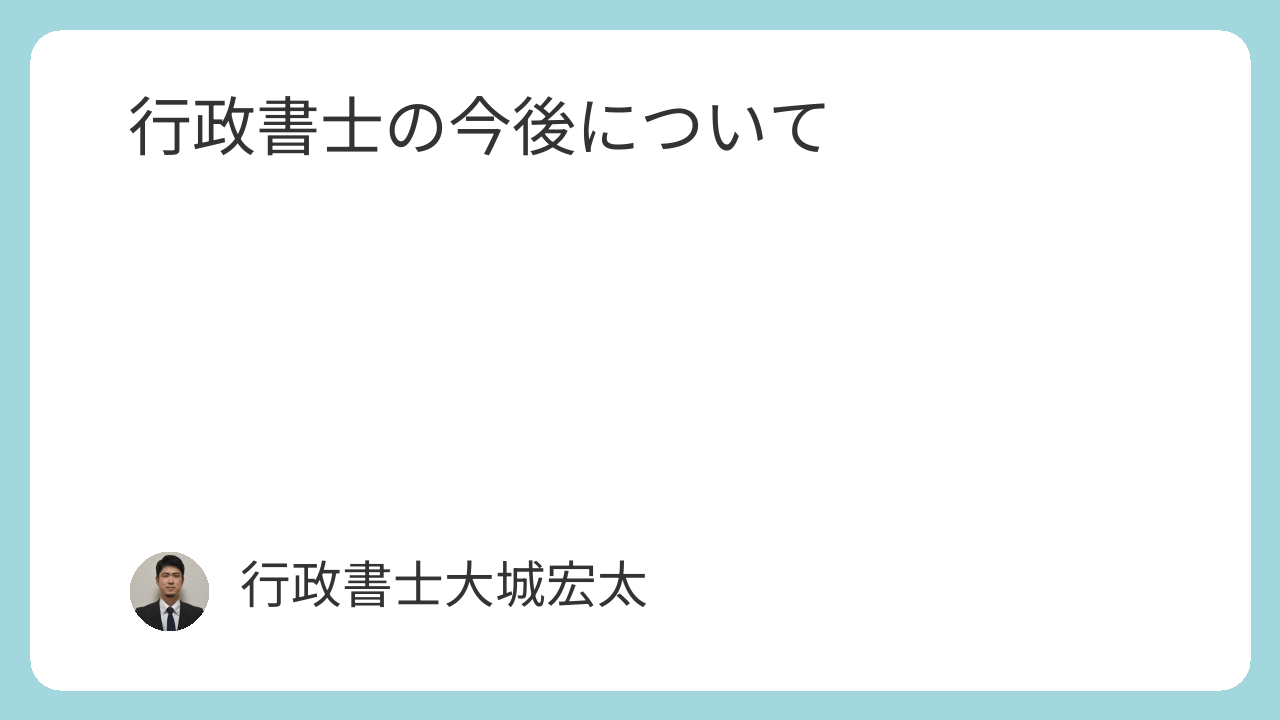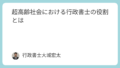こんにちは。沖縄で国際業務を中心に行政書士をしている大城です。
今回は初回の投稿ということで、「行政書士の今後について」というテーマで書いてみたいと思います。(※この記事は全部読んでも3分で読めます)
私が行政書士を目指した理由
私が行政書士になりたいと思ったきっかけは、外国人材の生活支援に関わる仕事をしていたことにあります。
その中で「在留資格の更新や申請も自分でサポートできれば、会社にいる間だけでなく、その後の人生にも寄り添えるのでは」と考えるようになりました。
「行政書士はコンビニより多い」は本当?
「行政書士はコンビニより多い」と言われることがあります。
実際には年によって多少前後しますが、全国の行政書士登録者数とコンビニの店舗数はおおよそ同じくらいです。
この事実を聞くと、「資格を取っても仕事がないのでは?」「開業してもやっていけないのでは?」と不安になる方も多いと思います。
仕事は本当にあるのか?
この問いに対して、開業間もない私があえて言わせていただきます。
「仕事は、あります。」
行政書士の業務範囲は非常に広く、
「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の作成等は行政書士の独占業務とされています。
加えて、行政手続の電子化が進んでおり、
「誰でもできる」と思われがちな申請も、実際には専門知識が必要になってきています。
つまり、行政書士の需要はむしろ増える可能性があると考えています。
また、AIの進化によって「行政書士の仕事はなくなるのでは」と言われることもありますが、私は逆だと思っています。
確かに定型業務の一部はAIに置き換えられるかもしれません。
しかし、AIを活用できる行政書士はより効率的に仕事ができ、顧客対応や提案力に時間を割けるようになるでしょう。
さらに、行政書士が担う仕事には、
- 顧客との信頼関係構築
- 地方自治体ごとの慣習への対応
- 外国人や高齢者の立場に立った調整・支援
といったAIには難しい、人にしかできない業務も数多く存在します。
仕事を“いただける”かどうか
「仕事はある」と言いましたが、
実際の課題は「どうやってその仕事をいただけるか」です。
私自身、開業したばかりで、まだ受任実績も少ない中、この課題に直面しています。
当然、実績や信頼がある先生に仕事が集中するのは自然なことです。
その中で、自分が選ばれるには:
- 基礎知識をしっかり身につけること
- AIや電子申請を使いこなせること
- 地域の課題や外国人支援などに強みを持つこと
といった努力が必要だと考えています。
ただし、行政書士には倫理規定や会則があり、
「他の行政書士の業務を妨害してはならない」
「品位を欠く勧誘行為は禁止する」
といったルールが明文化されています。
そのため、過度な直接営業や不適切なPRは懲戒対象になることもあります。
現実的な集客の道
だからこそ、地道に次のような方法を試みています:
- SEOやWebでの情報発信
- 他士業との連携
- 無料相談会への参加
- 名刺交換や地域へのご挨拶などの活動
行政書士は、士業でありながらサービス業でもあります。
自分の強みや経験を少しずつ伝え、信頼される存在になることが大切だと感じています。
最後に
この記事を読んで「行政書士を目指しているのに、不安になってしまった」と思った方がいたら申し訳ありません。
ですが、この考え方で本当にやっていけるのかどうか、これからもブログを通してお伝えしていけたらと思います。
なお、行政書士は全国に5万人以上います(コンビニと同じくらいです)ので、考え方も人それぞれです。
一つの意見として受け止めていただければ幸いです。
もしご相談やご依頼などございましたら、下記ホームページよりお気軽にお問い合わせください。