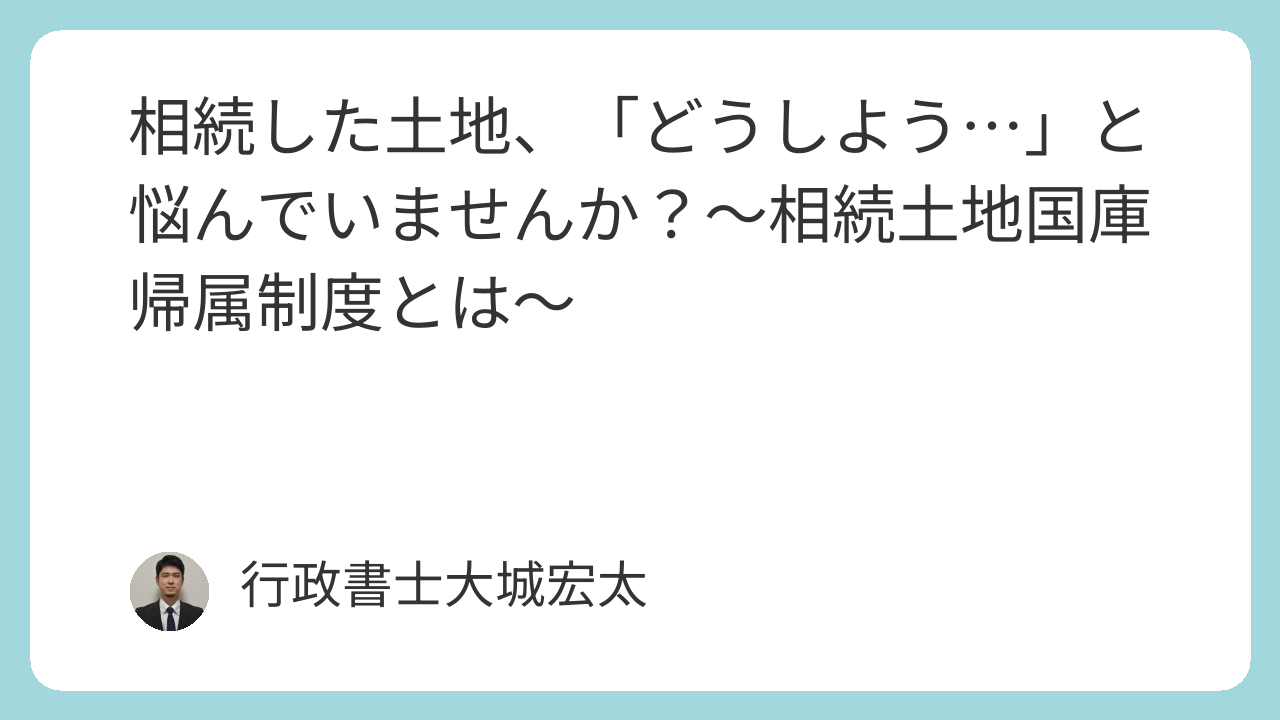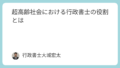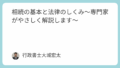相続で土地を取得したものの、使い道がなく管理に困っている方は少なくありません。固定資産税が毎年かかる、雑草や不法投棄のリスク、遠方にあるため管理が難しいなど、所有することが負担になっているケースが増えています。
こうした背景を受けて、令和5年4月から新たにスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
この記事では、行政書士の視点からこの制度の概要とメリット、注意点、そして手続きを円滑に進めるためのポイントを分かりやすくご紹介します。(※この記事はすべて読んでも3分程で読めます)
「国に返す」という新しい選択肢
この制度は、相続や遺贈(※相続人に対するものに限る)によって土地を取得した人が、法務大臣の承認を得ることで、その土地を国に引き渡すことができる制度です。
これにより、不要な土地の管理責任や税負担から解放され、土地の所有者不明化を防ぐことにも繋がります。
制度を利用するための3ステップ
相続土地国庫帰属制度を利用するには、大きく分けて以下の3つのステップがあります。
① まずは法務局へ相談予約
土地のある場所を管轄する法務局(本局)に電話または対面で予約を取り、相談を行います。相談の際には以下のような資料を持っていくとスムーズです。
② 承認申請書を提出
承認申請書を作成し、審査手数料(収入印紙)を添付して法務局に提出します。郵送でも可能ですが、対面の方がいいと思います。
必要な書類の一例:
(1)承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
(2)承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
(3)承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
(4)申請者の印鑑証明書(市区町村作成)
(5)相続人が遺贈を受けたことを証する書面
(6)土地の所有権登記名義人から相続又は一般承継があったことを証する書面など
③ 審査と承認
書類が受理された後、法務局が現地調査を行い、審査します。
承認されると「負担金の納付通知書」が届き、原則として1筆あたり20万円を納めます。
納付後に土地の所有権が国に移り、正式に土地の管理から解放されます。
対象外となる土地もある
制度を利用できる土地には条件があり、以下のような土地は申請できない、または承認されない可能性があります。
申請ができない土地の例
- 建物が建っている土地
- 他人の権利が設定されている土地(例:抵当権・地役権など)
- 通路や共用地になっている土地
承認されない土地の例
- 崖地
- 地上に撤去が必要な物(車、木など)がある土地
- 地中に埋設物がある土地
- 管理や処分に多大な費用・労力がかかる土地
制度の活用には専門家の力も
この制度はとても便利ですが、手続きや必要書類が多く、新しい制度のため1年以上の時間がかかることが多々あります。慣れていない方にとっては「何から始めていいか分からない」と不安になるかもしれません。
そんな時は、行政書士や司法書士、弁護士に相談・依頼することでスムーズに進めることが可能です。
まとめ:次世代に負担を残さないために
相続したけれど使わない土地を、「国に返す」という新しい選択肢ができました。
この制度を上手に活用することで、将来の税金や管理の手間を軽くし、次の世代に負担を残さない備えが可能になります。
とはいえ、手続きには専門的な知識が必要ですので、不安がある方はお気軽に行政書士までご相談ください。