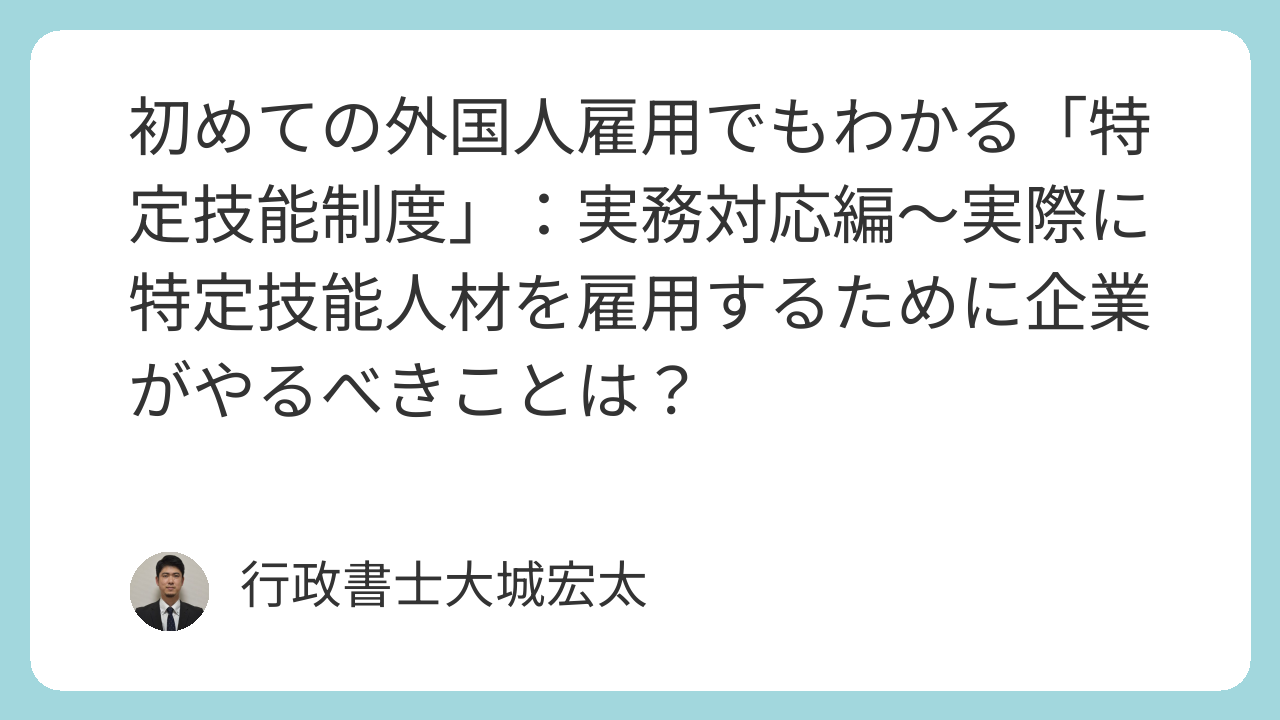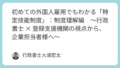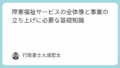はじめに
特定技能制度は、2019年に新設された比較的新しい外国人受け入れ制度です。現在では対象分野も拡大され、企業側の制度理解と受け入れ体制の整備がますます求められています。
この第2部では、外国人雇用が初めての企業様に向けて、実際に特定技能人材を採用・雇用するまでの流れや手続き、必要な準備や注意点などを、行政書士かつ登録支援機関の立場からわかりやすく解説していきます。
雇用までの流れと必要な手続き
全体の流れ
- 採用計画の立案(分野の確認、受入枠の検討)
- 求人・マッチング(国内外の候補者探し)
- 雇用契約の締結(労働条件の明示)
- 在留資格認定証明書交付申請(行政書士による支援可)
- 在留資格「特定技能1号」の取得
- 入国・雇用開始
- 支援計画の実施(登録支援機関または企業が対応)
あくまで全体の流れなので、別の機会でもっと細かく説明しようとおもいます。
企業が準備すべき書類(代表的なもの)
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 支援計画書(登録支援機関に委託する場合は委託契約書)
- 事業所概要書類(決算書、登記簿謄本など)
- 申請書類一式(在留資格認定証明書交付申請等)
などなど、必要に応じて行政書士または登録支援機関の担当者が教えてくれる資料を用意します。
登録支援機関とは?委託の有無でどう変わる?
登録支援機関とは
特定技能人材に対して「支援計画」に基づく生活支援・労働支援を行う民間事業者です。企業が自ら支援できない場合に業務を委託します。技能実習制度でいう「監理団体」が行っている場合や、行政書士が行っている場合もあります。
委託と自社支援の違い
| 項目 | 登録支援機関に委託 | 自社支援(企業自ら対応) |
|---|---|---|
| 支援の内容 | 生活支援、通訳、相談窓口などすべて代行 | 全ての支援業務を自社で実施 |
| 負担 | 委託費用が発生 | ノウハウや人員の負担が重い |
| メリット | 法令順守、専門性の確保 | コスト削減、社内での一体感 |
自社支援をするためには、外国人の受入れを適正に行えることを証明する資料を出さなければいけません。過去に実績がない場合や証明することができない場合は、最初は登録支援機関へ全部委託しましょう。
支援内容の例(義務的支援10項目)
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎対応
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 日本語学習の支援
- 相談・苦情への対応(多言語対応)
- 転職・解雇時のフォロー
登録支援機関の活用は、法令違反のリスクを避ける意味でも強く推奨されます。義務とされる10項目については、どの登録支援機関も必ずやってくれますが、任意とされる支援や金額などで差が生まれてきます。登録支援機関と契約する場合は、慎重に対面で相談や打合せをされることをお勧めいたします。
3. 採用時・雇用後に発生するコスト一覧
特定技能人材の受け入れには、通常の日本人雇用とは異なる特有のコストがかかります。
| 区分 | 主な費用 | 金額目安 |
|---|---|---|
| 採用時 | 紹介手数料(人材紹介会社) | 10万〜60万円/人 |
| 支援関連 | 登録支援機関委託料 | 月1.5万〜5万円/人 |
| 渉外 | 行政書士報酬(在留申請) | 10万〜20万円程度/件 |
| 入国準備 | 渡航費、住居保証、家具備品 | 10〜20万円/人 |
| 雇用後 | 日本語教育、通訳費用 | 月1〜2万円/人 |
| 更新手続き | 在留期間更新・書類作成 | 5万円前後/件 |
これらはあくまで一例であり、実際のコストは人材の出身国や雇用地域、業種などによって異なります。大人数の採用となれば1人あたりの費用は低くなってきますが、1人だと高くなってしまいます。また、費用は登録支援機関によって数万円変わる場合がございます。まずは、見積依頼をしてみるのがいいとでしょう。
4. 外国人材受け入れのメリットとデメリット
メリット
- 慢性的な人手不足の解消
若年層の労働力を確保できる - 定着率の高さ
真面目で安定した勤務が期待される - 多様性の促進
異文化交流による新たな気づき・職場改善の機会に
デメリット
- 言語や文化の違いによるミス・誤解
現場でのコミュニケーション不足がトラブルに直結 - 支援義務による負担
支援体制が不十分な場合、法令違反になるおそれも - 更新制限や在留資格の不安定さ
特定技能1号は最長5年まで。長期雇用には不向きな場合もある(※特定技能2号に進めば、無期限となる)
5. 受け入れ体制構築のポイント
(1)現場の理解と協力
- 日本人社員や現場リーダーへの事前説明会の実施
- 文化や宗教に対する配慮の共有(例:食事、休日)
(2)通訳・コミュニケーション手段の確保
- 多言語対応アプリやチャットツールの導入
- 日本語教育支援(学習教材の提供、学習時間の確保)
(3)住まいと生活インフラの整備
- 家具付き住宅の確保、保証人の手配
- 公共手続き(役所、銀行、携帯電話)のサポート
(4)メンタルケアとフォローアップ
- 定期面談や相談窓口の設置
- トラブル発生時の迅速な対応体制
6. よくあるトラブルとその対策
| トラブル例 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 突然の失踪 | 労働条件とのミスマッチ、孤立 | 雇用契約内容の明示、相談窓口の設置 |
| 日本語が通じない | 学習機会不足、指導法の未整備 | 日本語教育支援、ビジュアルマニュアルの活用 |
| 労働時間・休日の認識違い | 文化・制度の違い | 就業規則の翻訳、初期研修の徹底 |
| 住居近隣とのトラブル | ゴミ出しルール等の不理解 | 地域ルールの説明会開催、通訳支援 |
7. 行政書士・登録支援機関に依頼できること
行政書士が対応可能な業務
- 在留資格認定証明書交付申請の書類作成・申請代行
- 雇用契約や支援計画書の法令適合チェック
- 入管対応に関する助言
登録支援機関が提供する主な支援内容
- 生活オリエンテーションの実施
- 通訳・翻訳対応
- 住居確保、行政手続き支援
- 相談窓口、緊急対応
おわりに
特定技能制度は、単なる労働力確保にとどまらず、企業の国際化や多様性の促進にもつながります。その一方で、制度の理解不足や準備の不備がトラブルの原因となることもあります。
「受け入れて終わり」ではなく、「共に働き、育て、支え合う」体制づくりが、企業の持続的な成長につながります。
私たち行政書士・登録支援機関は、そうした企業の伴走者として、制度運用と実務支援を担ってまいります。この記事を通して、少しでも興味をもってくださった方、ご質問やご相談は下記ホームページより受け付けております。お気軽にどうぞ