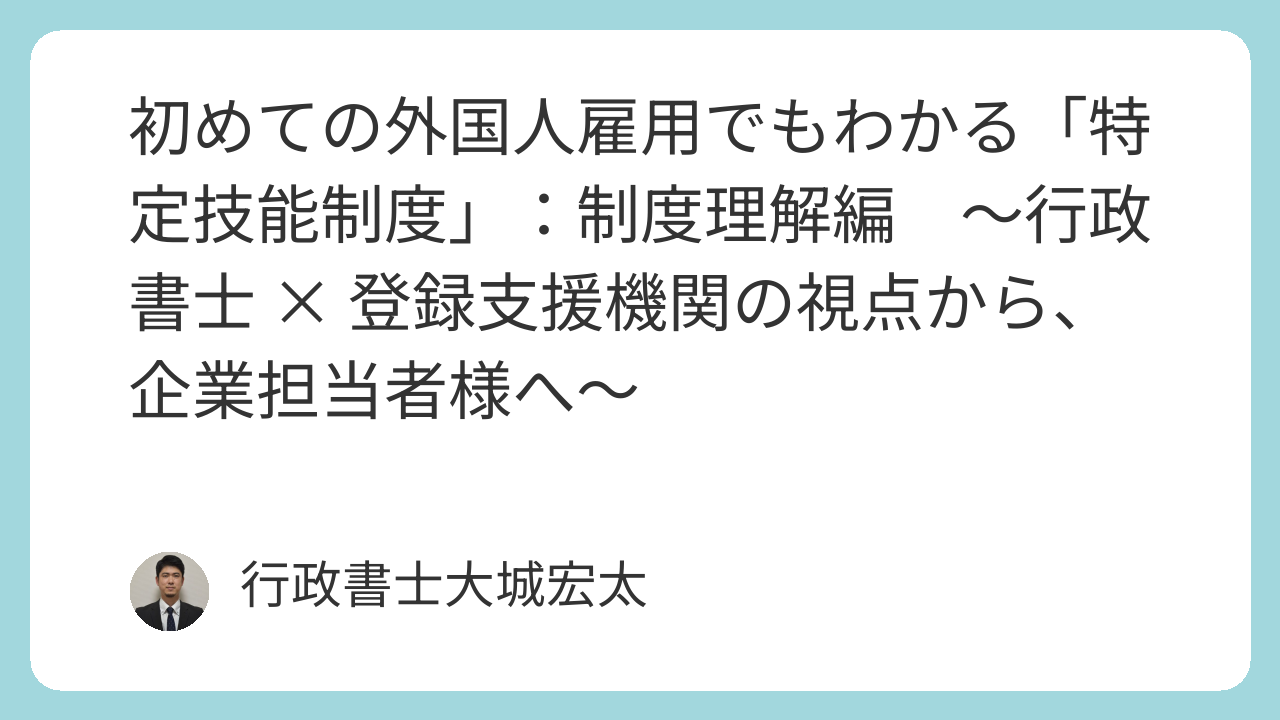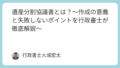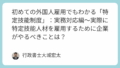はじめに:なぜ今、外国人材が必要とされているのか
日本国内では、少子高齢化による人手不足が年々深刻さを増しています。とりわけ、中小企業や地方の事業者様にとっては、若年層の人材確保が難しく、従業員の高齢化が経営課題となっているケースも少なくありません。
こうした背景を受け、国は2019年より「特定技能」という在留資格制度を創設しました。この制度は、一定の専門性・技能を有する外国人材が、日本国内で即戦力として働けるようにするものです。
本記事では、外国人雇用が初めての企業様を対象に、「特定技能とはどのような制度なのか」「どのような職種で受け入れができるのか」などの基礎的な内容から、今後の採用に向けて知っておくべきポイントまで、行政書士かつ登録支援機関の視点からわかりやすく解説してまいります。
特定技能とは?―制度の概要
「特定技能(とくていぎのう)」は、正式には**「特定技能1号」「特定技能2号」**という2つの在留資格を指します。
この制度の目的は、一定の専門性や技能を有する外国人材に、日本で就労する機会を提供することです。
2019年4月に新たな在留資格として創設されたこの制度は、それまでの「技能実習制度」とは異なり、人手不足の分野での労働力確保を主目的としています。したがって、外国人材が実際に「戦力」として業務に従事できるという点が大きな特徴です。
特定技能1号の概要
対 象: 相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する外国人
在留期間: 1年ごとの更新で最長5年まで
家族帯同: 不可
対象分野: 全16分野(外食業、建設、介護、農業など)
必要条件:・技能試験と日本語能力試験に合格していること、または技能実習2号を良好に修了していること
特定技能2号の概要
対 象: より熟練した技能を有する外国人
在留期間: 更新制(上限なし)
家族帯同: 可(配偶者・子の帯同が可能)
対象分野: 11分野(介護と新規追加された4分野を除く)※2025.6.11時点
必要条件:より高度な技能評価試験に合格していること
多くの企業様にとって、まず検討の対象となるのは「特定技能1号」になります。
特定技能1号と2号の違いを表で確認
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能レベル | 一定の技能 (業務に必要なレベル) | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 最長5年(1年・6ヶ月・4ヶ月更新) | 制限なし(更新可能) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能(条件付き) |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野 |
| 試験の要否 | 技能試験+日本語試験合格が原則 | より高度な技能評価試験に合格 |
対象となる16分野・業種の詳細とその特徴
2023年7月の時点で、「特定技能1号」の対象分野は12分野、そこに細分化された職種を加えると計14業種が存在していました。しかし、その後制度改正が進み、現在では「特定技能」の対象分野は合計16分野となっています。
現行の「特定技能」16分野
| 番号 | 分野名 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 介護 | ○ | × | 日本語能力要件がやや高い |
| 2 | ビルクリーニング | ○ | 〇 | 主に建物内の清掃業務 |
| 3 | 工業製品製造業 | ○ | 〇 | 金属加工や電気電子機器組立て、縫製など |
| 4 | 建設業 | ○ | 〇 | 土木、建築、ライフライン、設備など |
| 5 | 造船・舶用工業 | ○ | 〇 | 造船、船用機械など |
| 6 | 自動車整備業 | ○ | ○ | 自動車の点検・修理など |
| 7 | 航空業 | ○ | ○ | グランドハンドリング等 |
| 8 | 宿泊業 | ○ | 〇 | 接客、清掃など |
| 9 | 自動車運送業 | ○ | × | タクシー、バスなど(追加分野) |
| 10 | 鉄道 | ○ | × | 運輸係員など (追加分野) |
| 11 | 農業 | ○ | 〇 | 作物栽培・収穫 |
| 12 | 漁業 | ○ | 〇 | 養殖、漁獲など |
| 13 | 飲食料品製造業 | ○ | 〇 | 食品加工、製造など |
| 14 | 外食業 | ○ | 〇 | 調理、接客など |
| 15 | 林業 | ○ | × | 森林管理・伐採(追加分野) |
| 16 | 木材産業 | ○ | × | 製材・合板等の製造(追加分野) |
特定技能試験/日本語能力要件について
1.試験合格が基本ルート
外国人が特定技能1号で在留資格を取得するには、以下の試験に合格する必要があります。
- 技能試験(業種別)
- それぞれの分野ごとに試験が実施される
- 実施主体は厚生労働省や民間団体
- 実技・学科試験のいずれか、あるいは両方がある
- 日本語能力試験
- 基本は「日本語能力試験(JLPT)N4以上」
- もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」に合格
2.もう一つのルート:技能実習2号修了者
以下の条件に該当する場合、試験が免除される特例もあります:
- 技能実習2号を良好に修了していること
- 該当分野が一致している必要あり(例:農業実習→特定技能農業)
- 「良好な修了」の証明が必要
3.試験実施状況とスケジュール
各試験は日本国内および海外で定期的に実施されています。受験者数も年々増加傾向にあり、競争も激化しています。
技能実習との違いと誤解されやすい点
1. 制度目的の違い
| 制度名 | 目的 |
|---|---|
| 技能実習 | 「国際貢献」:開発途上国への技能移転 |
| 特定技能 | 「労働力確保」:即戦力人材の受け入れ |
特定技能は、**人手不足分野での「労働力としての受け入れ」**が明確に制度の目的として示されています。
2. 在留期間・家族帯同
| 比較項目 | 技能実習 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|---|
| 在留期間 | 原則3~5年 | 最長5年 | 無期限(更新可) |
| 家族帯同 | 不可 | 不可 | 可能(条件あり) |
3. 移行可能性とキャリアパス
- 技能実習2号→特定技能1号:可能(試験免除のケースあり)
- 特定技能1号→2号:ほとんどんの分野で可能(※) ※介護は、2号への移行ではなく、在留資格「介護」への移行という仕組みになっています。また、新規追加された4分野については、現時点では2号移行についての発表はありません。
4. 誤解されやすい点
- 技能実習の延長版ではない:制度の性質がまったく異なる
- 転職は制限あり:同一分野内であれば可能だが、変更手続きが必要
企業が守るべき基本ルール(法令・労働条件など)
1.労働法令の遵守
日本人と同等以上の労働条件を提供することが義務です。
- 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法など
- 労働時間・残業代・休憩時間の適切な管理
2.雇用契約と支援計画
- 特定技能外国人と締結する雇用契約は、フルタイム・直接雇用が原則
- 登録支援機関が行う支援業務(生活支援、行政手続き補助など)も企業の責任範囲
3.支援計画の提出と実行
- 企業自身が支援業務を行うか、登録支援機関に委託
- 支援計画は出入国在留管理庁に提出し、実施状況は監査の対象にもなる
4.不正行為への罰則
- 虚偽の申請や劣悪な労働環境などの不正が発覚すると、受け入れ停止や処分対象となります
- 不法就労助長罪や労働基準法違反での行政指導・刑事罰もあり
おわりに
ここまで、特定技能制度の概要や分野、在留資格の仕組みなどについてご説明してまいりました。制度の全体像について、少しでもご理解いただけたようでしたら幸いです。
ご不明な点や、貴社の業種が対象かどうかなど、具体的なご質問がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
おきなわ外国人サポート行政書士事務所 行政書士 大城宏太
次回は、実際に外国人材を採用・雇用するにあたって、企業として具体的にどのような準備が必要かを解説いたします。